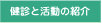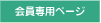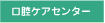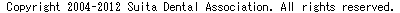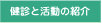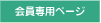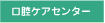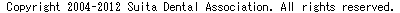| Q1 |
歯周病を予防するための歯みがきについて教えて下さい。 |
| A1 |
| 1. |
歯ブラシは、鉛筆を持つ持ち方と指先で持つ持ち方を、磨く場所によって使い分けるようにしましょう。 |
| 2. |
歯ブラシのあて方ですが、歯垢がたまりやすい場所は、歯と歯ぐきの境目です。そこに毛先を歯ぐきの方に向けてあて、やさしく磨きましょう。 |
| 3. |
歯間ブラシの使用は、歯と歯の間に隙間ができる年齢になれば必要になります。自己流では歯ぐきに傷を付けてしまうこともありますので、使い方やサイズは歯科医院で教わって下さい。 |
| 4. |
夜、寝る前の歯みがきは特に大切です。しっかり歯垢を取り除きましょう。 |
| 5. |
歯みがきする時間が取れない人には、入浴中の歯みがきがお勧めです。体温が上昇してから歯みがきすれば、血行も良くなりますので効果的です。 |
|
 |
 |
| Q2 |
3歳頃までの磨きかたのポイントを教えて下さい。 |
| A2 |
| 1. |
6ヶ月頃~1歳3ヶ月(前歯が生え始める時期)
乳児用歯ブラシを持たせ歯ブラシに慣れさせましょう。1日1回は仕上げみがき用歯ブラシやガ-ゼなどで歯を磨いてあげましょう。
|
 |
左:乳児用歯ブラシ
右:仕上げみがき用歯ブラシ
植毛部の大きさは同じですが、柄の長さが仕上げみがき用歯ブラシの方が長くなっています。
|
| 2. |
1歳3ヶ月頃から3歳(奥歯が生え始める時期)
朝と寝る前の歯みがき(できれば毎食後)を習慣づけましょう。保護者の方もいっしょに歯みがきすることが大切です。その後必ず仕上げみがきをしてあげましょう。2歳頃からはブクブクうがいの練習を始めます。
|
| 3. |
 仕上げみがきのやり方
仕上げみがきのやり方
寝かせみがきで、子どものお口の中がよく見えるようにします。むし歯になりやすいところ(奥歯の咬み合わせの溝、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目)を注意してみがいてあげましょう。
|
|
 |
 |
| Q3 |
3歳から6歳頃までの磨きかたのポイントを教えて下さい。 |
| A3 |
| 1. |
食べたら磨く習慣をつけましょう。 |
| 2. |
 保護者の仕上げみがきは必ず夜寝る前に行い、むし歯になりやすいところ(奥歯の咬み合わせの溝、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目)を、しっかりとみがいてあげます。むし歯になりやすいお子様は、フロス(糸ようじ)を使いましょう。
保護者の仕上げみがきは必ず夜寝る前に行い、むし歯になりやすいところ(奥歯の咬み合わせの溝、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目)を、しっかりとみがいてあげます。むし歯になりやすいお子様は、フロス(糸ようじ)を使いましょう。 |
| 3. |
むし歯になりやすいお子様には、フッ素入りの歯磨剤を使いましょう。 |
| むし歯になりやすいところ |
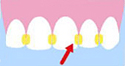 |
 |
 |
| 歯と歯の間 |
歯と歯ぐきの境目 |
奥歯の咬み合わせの面の溝 |
|
 |
 |
| Q4 |
小学校低学年の磨きかたのポイントを教えて下さい。 |
| A4 |
| 1. |
1~2年生の間はまだ仕上げみがきが必要です。 |
| 2. |
6歳臼歯が萌出する時期には、特に念入りな仕上げみがきが必要です。6歳臼歯は、頭を出してから完全に萌出するまでに何ヶ月もかかり、上下の6歳臼歯がきっちりと咬み合うまで1年半近くかかります。この間乳歯よりも背が低く、歯ブラシも届きにくいために非常にむし歯になりやすいのです。また、歯の溝も複雑で深く食べかすや歯垢がたまりやすいため、保護者の仕上げみがきがとても重要です。 |
| 3. |
歯と歯の間のむし歯を予防するため、できればフロス(糸ようじ)を使いましょう。 |
| 4. |
乳歯が抜け、歯ならびがデコボコになっている所は、歯ブラシを縦に当てて小さく動かしてみがきます。 |
 |
 |
| フロス(糸ようじ) |
6歳臼歯の位置 |
|
 |
 |
| Q5 |
小学校高学年の磨きかたのポイントを教えて下さい。 |
| A5 |
| 1. |
多くの乳歯が永久歯に生えかわり、6歳臼歯の後ろから12歳臼歯が生え始めます。12歳臼歯も6歳臼歯と同じ理由で萌出する時期には、特に念入りな歯みがきが必要です。 |
| 2. |
みがく事は自分で出来るようになっていますが、さぼり癖もつき始めます。本当にみがけているか、週に1回でもチェックしてあげましょう。 |
| 3. |
下の前歯の裏側(舌側)は歯石がたまりやすいので、歯ブラシのかかとを使って1本ずつみがきます。付いてしまった歯石は、歯ブラシでは取れませんので、年に2,3回は健診をかねて、歯医者さんでチェックしてもらって下さい。 |
|
 |
 |
| Q6 |
中学生以上の磨きかたのポイントを教えて下さい。 |
| A6 |
| 1. |
夜食を食べるなど、食生活も変化しています。就寝前の歯みがきをキチンと習慣化しましょう。 |
| 2. |
これからは、歯をいかに健康で長持ちさせるかが大切になってきます。毎食後の歯みがきはもちろん、フロス等で、歯と歯の間の清掃も十分に行って下さい。 |
| 3. |
むし歯だけでなく、歯肉炎の予防も大切になってきます。歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に当てるのがポイントです。軽く歯ぐきを圧迫しながら、その場所で、10回~20回ぐらい、毛先がほとんど動かないように細かく振動させます。 |
| 4. |
丁寧にみがくと、15分位はかかるはずです。歯磨剤はつけないか、ほんの少しでOKです。最初は鏡を見て、歯ブラシがきちんと当たっていることを確認しながらみがくと良いでしょう。夜、寝る前だけでも時間をかけてみがきましょう。 |
| 5. |
歯医者さんで、お口に合ったみがき方を指導してもらって下さい。また、定期健診をぜひとも受けて下さい。 |
|
 |
 |
| Q7 |
電動歯ブラシについて知りたいのですが? |
| A7 |
手で磨くこと(手動)に対して、電気で自動的に動く歯ブラシを『電動歯ブラシ』と呼んでいます。最近、様々な種類の『電動歯ブラシ』が販売されていますが、ブラシの動きと機能によって大きく3種類に分けることができます。
| 1. |
ブラシが電気で振動、あるいは回転する狭義の電動歯ブラシ
 ブラシの振動で歯についたプラーク(歯垢)を機械的に除去する歯ブラシです。手をあまり動かさずに、プラークを落とす機能を求めたもので、ブラシ全体が振動する「毛束振動式」、毛束が回転する「毛束回転式」、両者を組み合わせたタイプなどがあり、効果的にプラークを落とせるように工夫されています。 ブラシの振動で歯についたプラーク(歯垢)を機械的に除去する歯ブラシです。手をあまり動かさずに、プラークを落とす機能を求めたもので、ブラシ全体が振動する「毛束振動式」、毛束が回転する「毛束回転式」、両者を組み合わせたタイプなどがあり、効果的にプラークを落とせるように工夫されています。
|
| 2. |
ブラシが高速で振動する音波歯ブラシ
 1秒間に何回振動したかを表す単位をHz(ヘルツ)といい、人間の耳で聞き取れる領域の振動(16~20,000Hz)を「音波」と呼びます。 1秒間に何回振動したかを表す単位をHz(ヘルツ)といい、人間の耳で聞き取れる領域の振動(16~20,000Hz)を「音波」と呼びます。
音波歯ブラシは、ブラシの振動でプラークを機械的に除去する点では「狭義の電動歯ブラシ」と同じです。しかし、毎分30,000回という高速振動するブラシから発生する多数の泡沫により、毛先の接していない周囲2~3mmの部分までも刷掃効果がある、と云われています。この“音波効果”により、適切な場所に当てるだけでプラークを落とせるだけでなく、むし歯菌や歯周病菌の構造にダメージを与えるなどの効果が期待できるものです。
|
| 3. |
ブラシのヘッドから超音波の振動が発生する超音波歯ブラシ
 「超音波」とは人間の耳に聞こえる音波よりも高い振動数(20,000Hz以上)のことです。超音波歯ブラシは、ブラシのヘッド部分に超音波発生装置が内蔵され、超音波がブラシの毛先先端に伝わるようになっています。超音波には骨や皮膚の創傷治癒を促進する効果が確認されているため、歯周病の治りを促進し、予防的に働くことが期待されています。 「超音波」とは人間の耳に聞こえる音波よりも高い振動数(20,000Hz以上)のことです。超音波歯ブラシは、ブラシのヘッド部分に超音波発生装置が内蔵され、超音波がブラシの毛先先端に伝わるようになっています。超音波には骨や皮膚の創傷治癒を促進する効果が確認されているため、歯周病の治りを促進し、予防的に働くことが期待されています。
ただし、超音波だけではブラシの振動をほとんど感じませんので、プラークを機械的に除去するにはブラシの毛先を動かす必要があります。つまり、超音波歯ブラシとは、手用歯ブラシあるいは電動歯ブラシに超音波発生装置を組み込んだものといえるでしょう。
|
以上、それぞれの特徴を説明しましたが、購入の際はかかりつけ歯科医院で十分な説明と使用方法をお聞きになった上で、お使いください。
|
 |
 |
| Q8 |
糸ようじ(フロス)と歯間ブラシを使ったほうがいいですか? |
| A8 |
歯と歯の間を掃除するには歯ブラシだけでは不十分になりがちですので、できるだけ糸ようじ(デンタルフロス)や歯間ブラシを併用するようにしましょう。むし歯や歯周病の予防にたいへん効果的です。使い方を簡単に説明してみましょう。
| 1. |
糸ようじ(フロス)の使い方
| ① |
容器から30~40cm.の長さに切り出し、左右の中指(または人差し指)に両端を2~3回巻きつけます。
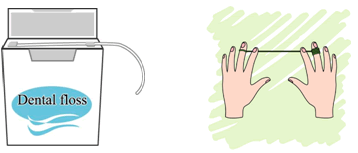
|
| ② |
親指と人差し指でつまんでピンと張り、歯と歯の間に滑らせながらゆっくりと挿入します。

|
| ③ |
歯ぐきの一番深いところまで入れ、歯の側面に押し付けるようにして、こすりながら2~3回上下させます。
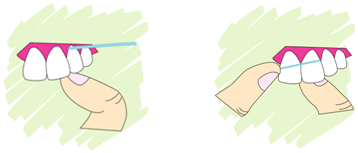
|
| ④ |
汚れたフロスは一方の指に巻き取り、順次新しいフロスで操作を繰り返します。
指先で操作するのが難しい方は、U字型やY字型のホルダー付きタイプもありますのでお試しください。
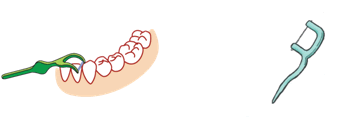 |
|
| 2. |
歯間ブラシの使い方
| ① |
歯間のサイズにあった太さの歯間ブラシを選びます。
歯間に通した時に、きついと感じない程度に余裕のあるタイプを選んでください。
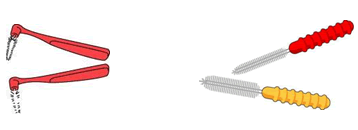
|
| ② |
ブラシは曲げずに、ゆっくりと歯間に挿入します。
ブラシの先で歯や歯ぐきを傷つけないように、ゆっくりと歯間に入れましょう。狭いところに無理に挿入すると歯や歯ぐきを傷つける恐れがあります。慣れないうちは鏡を見ながら使いましょう。

|
| ③ |
歯と歯ぐきの境目にブラシの毛先が当たるようにして、細かく前後に動かして清掃します。
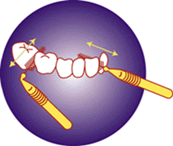 使いはじめに出血することがありますが、これは歯ぐきが炎症を起こしているためです。使用を続けることによって、炎症は治まり出血しなくなっていきます。
使いはじめに出血することがありますが、これは歯ぐきが炎症を起こしているためです。使用を続けることによって、炎症は治まり出血しなくなっていきます。
また、歯ぐきの腫れが引くと歯と歯の間に隙間ができたり、歯が長くなったように見えることがありますが、これは歯ぐきが引き締まって健康な状態に戻ってきた証拠ですので心配ありません。
いずれも、かかりつけ歯科医院で正しい使用方法などの指導を受けた上で使うようにしてください。
|
|
|
 |